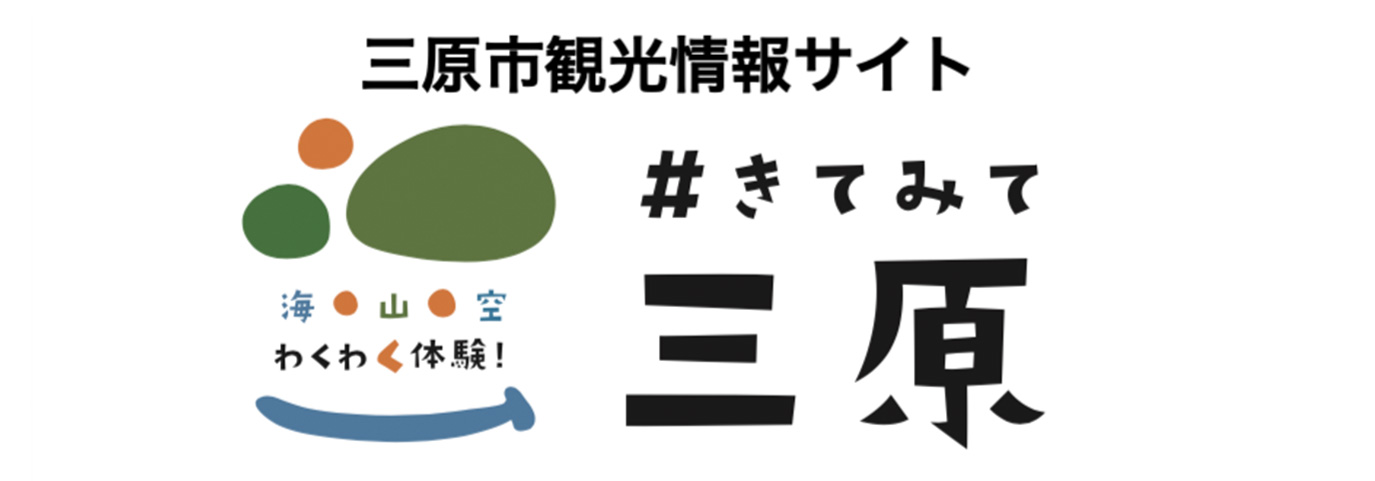-
期待と不安を抱えて ― 若者17人が自分の将来と向き合った3日間
都市部の若者が三原のまち・ひと・しごとに触れ、社会課題に向き合うことで、関係人口の創出と地域人材育成をめざす「三原“志”育成キャンプ2025」が、令和7年8月15日~17日の3日間に開催されました。
神戸大学・広島大学の学生と社会人OB計17名が参加し、地域起業家や自治体職員計12名が有志で協力しました。
プログラムの流れ
1日目:社会課題や地方創生の事例を学び、三原の現状をインプット。夜は交流BBQで打ち解ける
2日目:午前は川遊びで自然に触れ、午後は空き家再生・行政DX・人材育成・AI/DAO活用の4分野に分かれてフィールドワーク。夜は焚き火トークで本音を語り合う
3日目:学びを言葉にする「志ピッチ大会」で17人全員が発表、7人の地域起業家が講評。
多くの参加者にとって三原は初めての土地でしたが、なぜ足を運んだのか?
神戸大学経済学部3年の杉浦さんはこう振り返ります。
「大学生NPO団体(アイセック神戸大学委員会)で70人をまとめていますが、“社会課題に挑むロールモデル”に出会う機会は少なかった。地域の起業家と直接話せると聞き、迷わず三原行きを決めました。距離は遠いけれど学びがあると思ったんです。…ただ、遅刻しましたけどね(笑)」
若者らしいエピソードを交えつつ始まったキャンプは、初日から熱気に包まれていきました。 -
とある移住者の挑戦から ― 三原を"若者のキャリア形成"の舞台へ
今回の合宿を企画したのは、情報通信会社で事業開発を担い、令和5年に三原へ移住した藤澤未雪さん。これまでに19組59名を招き、延べ149日の滞在をコーディネートしてきた経験から、「三原には、リアルな社会課題を体感できる学び場としての可能性がある」と確信し、このキャンプを立ち上げました。
藤澤さん自身も、都会時代には「自分がいなくても街は回る」という感覚に迷いを抱いていました。しかし三原では、「自分が動かなければ困る人がいる」という現実があり、そこに"挑戦"と"役割"を見出したといいます。
「地域での事業創出は都会よりも難しい。だからこそ本物のアントレプレナーシップが試され、その熱気に触れることが若者の成長につながると思った」――この思いが合宿の出発点でした。
また、三原への来訪が3度目となる社会人OBの阪下さん(フリーランス・30歳)も語ります。
「最初はリゾート気分で訪れましたが、こんなに熱い大人たちがいるとは思わなかった。遊びながら気づきも得られるのが三原の魅力。だから3回もリピートしても飽きることがないんです」
若者の好奇心と起業家の実践知が交わる場。その共創こそが、三原の強みを示しています。 -
12人の地域起業家から学ぶ ― 社会課題のリアルに触れる
合宿初日は、日本全体が直面する社会課題や地方創生の先進事例を学び、三原市の現状や挑戦について幅広くインプットが行われました。
2日目には「社会課題フィールドワーク」を実施。参加者は空き家再生、行政DX、地域商社、AI・DAO活用の4分野に分かれ、現場で挑戦する起業家と直接対話しました。
特に印象的だったのは、地域おこし協力隊として令和4年に三原へ移住し、空き家再生や地域商社の立ち上げに挑む坂江隆太さんの姿です。縁もゆかりもない土地で「三原に貢献する」という使命感を持ち、任期終了後も地域に残って事業を継続する覚悟は、学生たちの心を大きく揺さぶりました。
神戸大学経済学部3年の丸山さんはこう語ります。
「坂江さんのように一貫して志を持ち続け挑戦する姿が本当にかっこいいと感じました。私はまちづくりに関心があり、不動産デベロッパー業界を志望しています。将来は官民が一体となった再開発に携わり、日本を元気にしたい。そのためにも使命感を持って自分軸を磨き続けたいと思いました」
フィールドワークでの出会いは、単なる知識習得にとどまらず、学生が「自分は何を軸に生きるのか」を考える契機となりました。 -
学生だけでなく社会人OBも ― 17人全員に火がついた最終発表会
合宿最終日のハイライトは、参加者一人ひとりが三日間の学びを言葉にする「志ピッチ大会」でした。2日目の夜には、涙を流しながら語り合い、気づけば朝5時半まで壁打ちを続けた学生もいたほど。迷いを吐き出し、仲間や大人と真正面から向き合った時間が、最終日のステージへと結実しました。
神戸大学法学部3年の三原さんは、涙をこらえながらこう語ります。
「凄すぎる大人や仲間に出会って、自分が分からなくなった瞬間もあった。けれど、その中で揺るがない想いを見つけました。私は広島が大好きで、地元に貢献したい。その気持ちは変わらない。これからは自分の強みを磨き、もっと誇れる形で還元していきたい」
彼女を支えたのは、夜通し寄り添った移住者の有志でした。地元への貢献を胸に令和4年に三原にJターン移住した伊藤健志さんは言います。
「行政でキャリアを歩もうとする彼女に、自分の若い頃を重ねた。未来の同志に出会えた気がしたし、私自身も学ばせてもらった。こういう場があるから、地域の大人も磨かれ続けるのだと思う」
学生と大人が互いに刺激し合い、キャリアと地域貢献への想いが共鳴する瞬間――それこそが、この合宿の最大の価値を示していました。 -
笑いと自然に包まれた3日間 ―全員が「また三原に来たい」と回答
合宿の三日間は、ただ真剣に学ぶだけではありません。川遊びに恋愛トーク、夜の花火にカラオケ大会と、笑いが絶えない瞬間がいくつもありました。
神戸大学工学部2年の後藤さんはこう振り返ります。
「最初は“おカタい勉強合宿”だと思っていました。でも川では童心に戻ってはしゃぎ、夜は仲間と恋愛や将来を本音で語り合った。最近は自分らしさを出せず悩んでいましたが、三原で仲間や大人に出会い、地方創生に挑戦したいという想いを再確認できました。それも“楽しんでやればいい”と気づけた。漠然と苦しかった心が、また前を向けるようになったんです」
楽しさがあったからこそ、学びが心に刻まれた――これは参加者全員に共通する実感でした。アンケートでは17人全員が「三原の印象がすごく良くなった」と回答し、全員が再訪を希望。その内訳は「必ず来たい」が約7割、「機会があれば」が約3割でした。さらに4割が「副業やインターンで関わりたい」と答え、3名は「2拠点居住や移住を検討したい」と意欲を示しました。
都会では得難い学びと、自然と人に囲まれた時間。その両輪が、若者の意識と行動変容を確かに後押ししていました。 -
DAOで広がる未来 ― デジタルでつながる新しい関係人口の形
「来年も三原で合宿をしたい」という声が広がる中、企画を担った神戸大学文学部2年の桶田さんが代表して宣言しました。
「次年度も必ずやらせてください!」
その関心を一過性で終わらせず、継続的な関与へと変える仕組みとして導入されたのが、㈱まちづくり三原が進める machiducrew DAO です。DAO(分散型自律組織)とは、インターネット上で「誰が参加しても、合意形成しながらプロジェクトを進められる仕組み」。ブロックチェーン技術を活用することで、参加者の貢献を記録し、透明性を保ちながら継続的に活動できます。今回のキャンプでは修了証書をNFTとして発行し、単なる記念品ではなく、合宿後も学生と三原を結ぶ「デジタルの絆」として機能します。
広島大学総合科学部1年の小林さんはこう語ります。
「私は地域おこしだけでなく、国際交流や平和教育など関心の幅が広いです。学生としていろんな場所に足を運ぶ中で、必ずしも現地に行かなくてもスマートフォンから地域づくりに関われる仕組みがあるのは、とても面白いと感じました」
リアルな出会いとデジタルの継続接点。その両輪が、若者の意欲を未来へと確かにつなげています。 -
地域だからこそ人が輝く― 三原発・若手人材育成モデルへの展望
焚き火を囲んで涙を流した学生も、清流ではしゃいで笑った学生も、最終日には胸を張って自分の想いを語り、拍手に包まれて三原を後にしました。
主催の藤澤未雪さんは静かに語ります。
「都会では、あなたが欠けても街は回る。けれど地方には“あなたが関わらなければ動かない課題”があります。だからこそ挑戦者が輝ける。三原で学生とOBたちが想いを見つけ、満足げに帰っていく姿に、この街の未来への確信を持てました」
人と自然と未来が交わる街・三原。ここから芽生えた若者たちの想いが、地域とキャリアを結びつける新しい人材育成モデルとなり、社会をより良く変えていくことを願って…。
イベント名:三原“志”育成キャンプ2025
日程:2025年8月15日(金)~17日(日)
会場:三原市役所、まちづくり三原、和木ふれあい交流センター、ゲストハウスHaku、SATELASSほか
主催:藤澤未雪(三原市移住者有志)
協力:起業家有志、移住者有志、自治体職員有志 計12名(清水逸志〈三原市〉 、浦谷佳孝〈AI DARUMA〉 、滝口翔太〈ゲストハウスHaku〉、竹谷力〈爆上げサンタ〉、奥田若奈〈結婚•婚活サポート harunohi〜ハルノヒ〜〉、伊藤健志〈広島県庁〉、川内文香〈バルーンショップbunbun〉、佐藤梓〈しまなみ三原〉、坂江隆太〈地域おこし協力隊〉、泉太貴〈まちづくり三原〉ほか)
映像:[三原“志”育成キャンプ2025のダイジェストはこちら]
-
お問い合わせ
Contact
-
移住を検討中の方は
こちら -
サイト内検索
Search
-
各種SNS
Sns